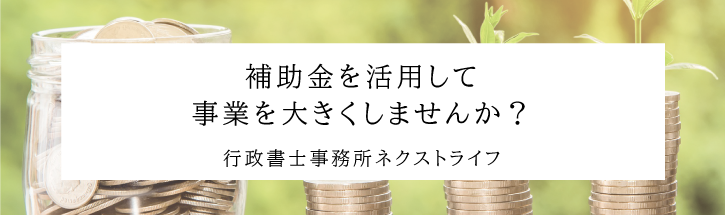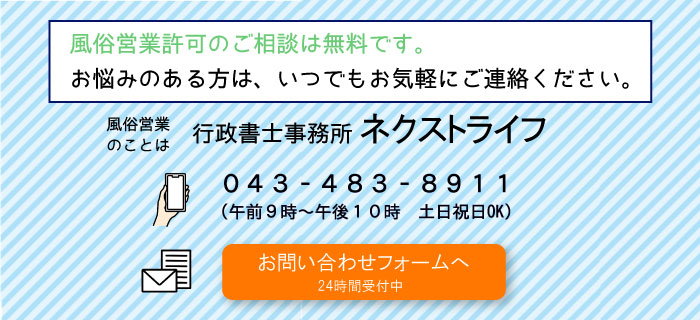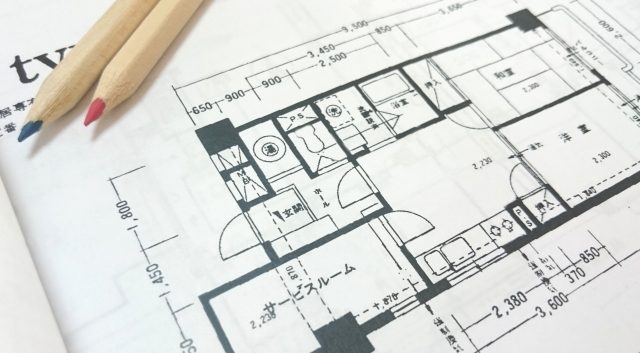風営法専門の行政書士は先に確認する、風俗営業を行う場所の「用途地域」
行政書士事務所ネクストライフでは、毎月定期的に風営法の手続き・・・風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを行っておりますが、お客様からご相談を受けた際に、まず先におたずねすることがあります。それは「店舗の住所はどこですか?」ということです。
風俗営業は、行える場所、行えない場所がある
風俗営業を行う場合、「これから私は風俗営業をやろう!」と思い立ってすぐにできるものではありません。いろいろな要件をクリアして手続きをしたうえで「風俗営業許可」を取得しないとは風俗営業を行うことができません。
その中でも特に( 風俗営業許可の要件の中で1番 )注意しないといけない「場所」です。
「場所」の問題をクリアするためには「2つの項目」を見る必要がある
この「場所」の問題をクリアするためには「2つの項目」から、風俗営業を考えている店舗周辺の状況を調査しなければなりません。
まずは「用途地域」です。
用途地域は各市区町村によりいろいろな形成をされています。その地域の事情により、どの地域をどのようにあ開発していくか、開発していかないか、地域により反映されています。そのため風俗営業のような地域に影響が出かねない営業については、一定の用途地域でしか営業ができないよう、風営法や関係法令で制限されています。
もう1つは「保全対象施設」。
保全対象施設とは「その利用者のために特に配慮しなくてはならない施設」のことを言います。例であげると小学校、中学校、高校、大学、病院、児童福祉施設、図書館・・・・、などなどいろいろな施設があります。この保全対象施設から一定の距離の中に、風俗営業を行うお店があってはいけません。
もしもその一定の距離内にお店があれば風俗営業許可を取得することはできないので、ずっとそこの場所では風俗営業を行うことはできません。
保全対象施設の詳しいご案内は下記の記事をご覧ください。
 風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
用途地域とは
「用途地域」とは「市街化の計画」や「その地域の事情」を考えて、それぞれの市区町村が指定した地域のことをいいます。
例えば住宅系の地域であったり、商業系の地域、工業系の地域何かがあります。用途地域は全ての場所にてしてされているわけではなくて「このエリアは指定しなくては!」と選択して指定されています。
多くの場合、「駅」の周辺に「商業地域」「近隣商業地域」が広がります。そして「商業地域」「近隣商業地域」の周辺に住居系の地域が指定される、というパターンが多いです(もちろん例外もあります)。
風俗営業ができない用途地域
風営法についての「都道府県条例」には、風俗営業ができない地域が定められています。
千葉県・埼玉県の風営法条例では「第一種地域」などと区別されていますが、それ以外の地域では違う名称であることもあります。しかし、その内容を見ればほとんどの場合、住居地域における風俗営業はできないということで共通しています。
住宅地が広がる地域で接待ありのキャバクラやガールズ・バー、スナックなどを経営するのは地域社会にとって良くないですよね。こどもの教育や家族の平穏な暮らし、そういった事情を考えたとき「下記のような地域で風俗営業を行ってはいけませんよ!」という風営法でのルールがあるわけです。
具体的には下記の通りです。
【風営が禁止されている主な住居地域】
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
上記の用途地域の説明は下記の通りです。
(参考:国土交通省:みんなで進めるまちづくりの話)
| 第1種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域です。 小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 |
|---|---|
| 第2種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域です。 小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。 病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域です。 病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
| 第1種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
| 第2種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。 |
| 準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
上記をご覧いただけると分かるように、これら地域において風俗営業を行った場合には、地域によくない影響が出ることがうかがえます。
「住宅のための地域」「住環境を守るための地域」そんな言葉が説明の中にたびたび出現するような地域なわけですから、風営法ではこういった地域での風俗営業を規制しているわけなのです。

住居が広がる地域で、風俗営業を行うお店を借りるのは危険です。必ず用途地域の確認をしましょう。
風俗営業ができる用途地域
風俗営業ができる用途地域は以下の通りです。
こういった地域は幹線道路沿いでしたり、駅の周辺に広がっていることが多いです。
特に、接待行為が行われているであろうお店や、パチンコ店、マージャン店がある地域は下記のような用途地域が広がっている可能性があります。
【風俗営業ができる用途地域】
商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
指定のない地域
上記の用途地域は下記の通りです。
(参考:国土交通省:みんなで進めるまちづくりの話)
| 商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。 住宅や小規模の工場も建てられます。 |
|---|---|
| 近隣商業地域 | まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
| 準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
| 工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。 住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
| 工業専用地域 | 工場のための地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
要するに、上記のような地域は「商業化」「工業化」が著しい地域です。このような場所では風俗営業が許されています。
ただし、いくら用途地域上は風俗営業が大丈夫だといっても「保全対象施設」から一定の地域内では風俗営業ができませんのでご注意ください。

駅の周辺には、商業地域や近隣商業地域が広がっているケースが多いですが、エリアが狭かったり、東口には広がっているのに、西口には住居地域しかない、というケースもあります。十分お気をつけください。
他の法律で、風俗営業が制限されることもあります
風営法の手続きなのですが、他の法律・・・例えば建築基準法で風俗営業が制限されるケースがあります。
建築基準法では、用途地域別に建築可能な建物・建築物について説明がされていますが、「風営法」で許されている地域なのに「建築基準法」では風営法を行う建物として建設できない建物があるのです。
「風営法」でも許され「建築基準法」でも許されている地域は「商業地域」「準工業地域」のみしかありません。
ですから例えば、近隣商業地域のお店で風俗営業1号許可が発行されたとしても「建築基準法」からの指導がある可能性は残ります。
用途地域がわからなければ、迷わず風営法専門の行政書士に相談した方が無難です
用途地域を間違えて風俗営業のための店舗を借りたとき、風俗営業許可の申請をしても、許可が下りることは絶対にありません。
場所を間違えてしまうと、どんなにお金をかけれたとしても絶対に風俗営業許可を種痘することはできないのです。
ですから、風俗営業ができるお店かどうか不安な場合は、風営法専門の行政書士に相談した方が安全です。行政書士事務所ネクストライフは、風営法の相談・助言は基本的に無料で行っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。